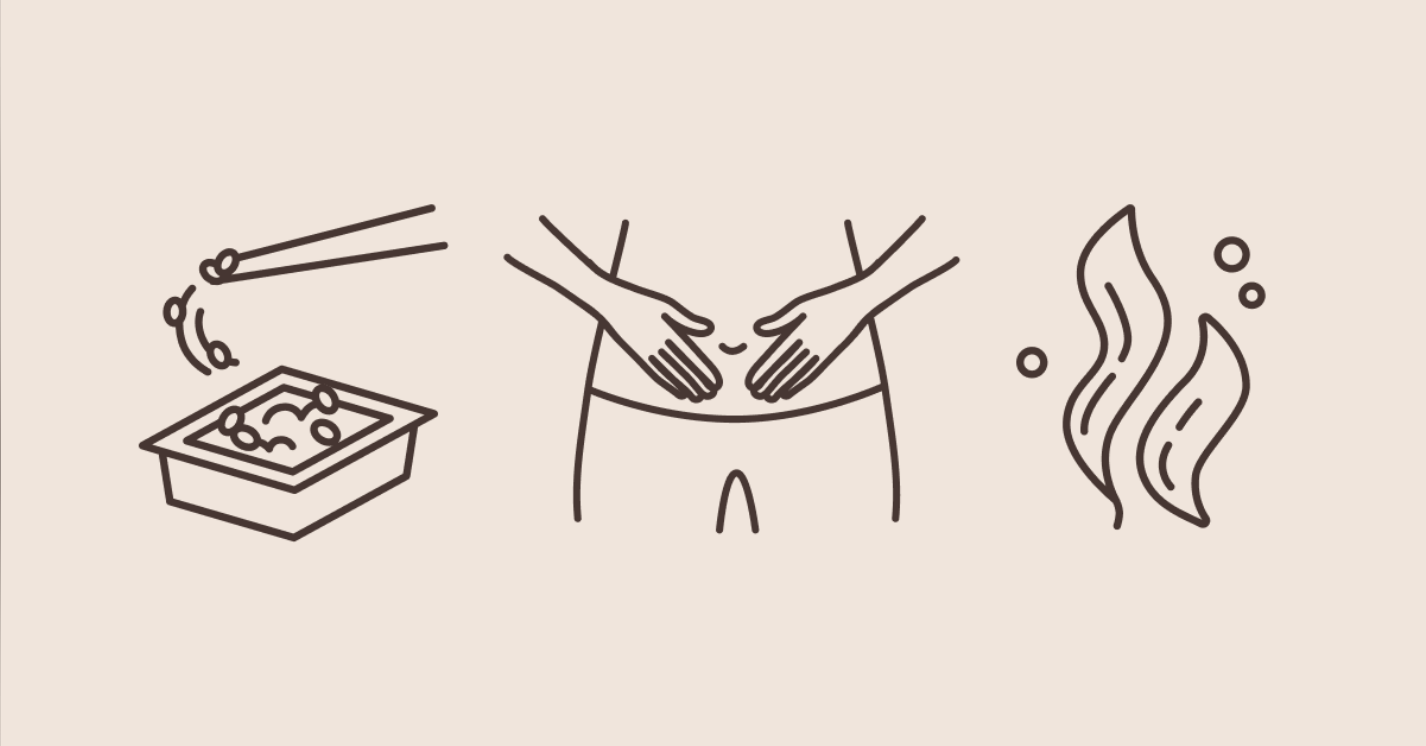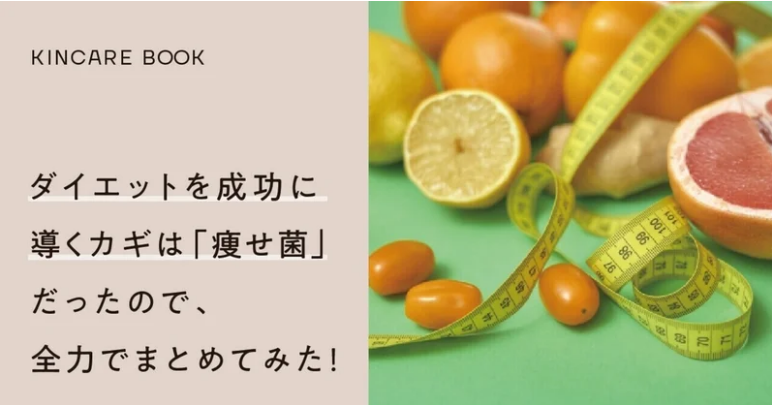お酒を飲んで下痢するのはなぜ?腸活目線で選ぶお酒4選

そんなお悩みを抱えている方は実は多いようです。
お酒を飲むことで腸がトラブルを抱えるのは、アルコール、糖質、冷えが3大要因と考えられています。
もちろんアルコール自体、飲みすぎは色々な意味でよくないですが…。
小腸と大腸にかかる負担の仕組みを知れば、お酒の選び方や飲み方で負担を軽減できる余地はあるかもしれません。
今回は、適量の摂取を大前提に、菌ケア(腸活)を考えるなら何を飲む?というお酒の選び方について考えてみました。
お酒を飲んで下痢になるのはなぜ?

お酒を飲んでお腹を下したこと、ありませんか?
なぜ飲酒で下痢を引き起こしてしまうことがあるのでしょうか。
まず腸は、排泄だけでなく、食べ物を分解して栄養として体内に吸収する器官でもあります。
食べ物や飲み物が摂取されたとき、消化・吸収・排泄・合成・免疫・浄血・解毒…と、大忙しに働き続けるのです。
そして消化によって分解された消化物から、糖やアミノ酸、脂肪酸、水分など、身体をつくるのに必要な栄養素を吸収。
そのなかで、アルコールの場合は胃で約20%、残りの約80%は腸(小腸)で吸収されます。(※1)
お酒を飲み過ぎると、どうなるのか?
それではお酒を飲み過ぎるとどうなるのでしょう。
お酒自体の糖質もさることながら、おつまみなど塩分の多いものや甘い味付けのものなども含む、水分を取り込もうとする浸透圧の高いものが腸に残ります。
その結果腸が本来おこなう水分の吸収を妨げ、腸内の水分量が過剰な状態に。
さらに約80%のアルコールや食べ物を消化吸収するはずの小腸では、粘膜の働きが弱まり十分な消化をできなくなります。すると、小腸で消化しきれなかった食べ物などがそのまま大腸へ流れ込むことに。
大腸では、いつもより多い水分量に加え、小腸で不十分な消化状態の食べ物が合流し大きな負担になっています。
体の外へできるだけ早く排泄しようとして、蠕動運動が活発になり、これが下痢の症状となるのです。
体質などにより他の原因もあり得ますが、これが飲酒で起こる下痢の原因として多いと考えられています。(※1)
飲み過ぎは大腸がんの原因にも
飲酒と大腸がんの関連性はこれまでも指摘されてきました。
国立がん研究センターによると、欧米人に比べて日本人はお酒に弱い遺伝子タイプを持つ人が多く、飲酒による健康影響を受けやすいために大腸がんのリスクも高いことが発表されました。(※2)
飲酒が大腸がんを引き起こすメカニズムについて現時点でまだはっきりとは判明していませんが、アルコールを摂取することで生じるアセトアルデビドという代謝産物に発がん性があることが指摘されています。
さらに、このアセトアルデビドが葉酸の働きを阻害することで、発がんの初期段階に見られる遺伝子異常である低メチル化が引き起こされるためという考えが有力視されているのです。
近年、日本では大腸がんをはじめとした発がん率の増加が問題になっており、お酒の飲み過ぎを防ぐなど、生活習慣の見直しが必要と考えられています。
15g飲酒量が増えるごとに大腸がんのリスクは10%増
アルコールの摂取量が増えると、さまざまな健康リスクが高まることが知られています。特に、大腸がんのリスクに関しては、15gの飲酒量が増えるごとにリスクが約10%増加することが報告されています。この数値は、国立がん研究センターが提供するデータに基づいており、飲酒と大腸がんの関連性を明確に示しています。(※3)
国立がん研究センターのウェブサイトによると、飲酒が大腸がんの発生リスクを高めることが複数の研究で確認されています。以下にその調査結果の概要を示します。(※3)
調査期間:数十年間にわたる追跡調査
結果:15gのアルコール(ビール中瓶1本程度)を追加で摂取するごとに、大腸がんのリスクが10%増加
健康を維持するためには、アルコールの摂取量を適度に管理することが重要です。日本では、男性は1日あたり20g以下、女性は10g以下のアルコール摂取が推奨されています。これは、ビール中瓶1本(約500ml)またはワイン1杯(約120ml)に相当します。
毎日お酒を飲んでいる方は、1週間のうち何日か休肝日を設けたり、ノンアルコールドリンクを活用してみるのもおすすめです。
お酒による下痢はいつ治る?

お酒を飲み過ぎて下痢を引き起こした場合、一般的には数日間で回復することが期待されますが、
個人の体質や飲酒量によっても異なります。
万一、下痢が長引く場合や、脱水症状やその他の深刻な症状が現れる場合は、他の病気が隠れている可能性もあるため、
自己判断で放置せず医師に相談することをおすすめします。
お酒が抜けるまでの時間
お酒を飲んだ後、体内からアルコールが完全に抜けるまでの時間は、飲んだ量や個人の代謝速度、体重などによって異なります。一般的には、アルコールの分解は肝臓で行われ、平均的な速度で代謝されます。
アルコールの代謝速度
平均的には、健康な成人は1時間に5~7gのアルコールが分解できます。これは、ビール350ml(アルコール5%)に含まれる約14gのアルコールを分解するのに、約2~3時間かかる計算です。
※代謝速度は、年齢、性別、体重、飲酒習慣、肝臓の健康状態などにより異なります。たとえば、男性は女性よりも代謝が速い傾向があります。
お酒が抜けるまでの時間を短縮するための即効性のある方法はありませんが、以下の対策を講じることで、アルコールの影響を最小限に抑えることができます。
・十分な睡眠を取る
下痢を早く治すためには
飲酒が原因ので下痢になってしまった場合、まずは下痢による脱水症状を防ぐために水分補給をこまめにするようにしましょう。
下痢をしている時、これ以上便を緩くしないためにと水分を控える人もいますが、下痢によって体内の水分がどんどん奪われているため危険です。
水やスポーツドリンクなどで適切な水分補給を心がけてくださいね。
飲み過ぎで下痢になっている時は、胃腸はダメージを負って疲れています。胃腸がしっかりと休息をとるためにも、食事は温かいお粥など脂質や刺激が少なく、消化の良い腸活目線の食べ物を選ぶと良いでしょう。
下痢が落ち着いてからも、しばらくはいつも以上にバランスの取れた胃腸に優しい食事を続けることが大切です。
下痢が続く場合は、薬局で手軽に購入できる抗下痢薬を使用するのも一つ。電車での通勤途中や仕事中の急な下痢には、水なしで飲める下痢止め薬があるとお守り代わりになります。
それでも良くならない場合や下痢が長引いたりその他の症状が現れる場合は、医師に相談するようにしましょう。
お酒で下痢をしたら太らない?

飲酒後に下痢を経験する人は少なくありません。そのため、「下痢をすれば摂取したカロリーも排出されるのではないか」と考える人もいるかもしれません。しかし、実際には下痢が体重やカロリー摂取に与える影響は限られています。
カロリーの吸収は小腸で行われる
食べ物や飲み物に含まれるカロリーは主に小腸で吸収されます。お酒も同様で、アルコールやそれに含まれるカロリーは小腸で速やかに吸収されます。そのため、飲酒後に下痢をしても、すでに吸収されたカロリーは排出されず、体内に残ります。
一時的な体重減少は、主に水分の喪失によるもので、脂肪やカロリーの減少ではありません。下痢による体重減少は一時的であり、通常は水分補給によりすぐに回復します。
また、頻繁な下痢は、体の水分バランスを崩し、電解質の不足を引き起こす可能性があります。これにより、脱水症状や体調不良を引き起こすリスクが高まります。特に飲酒後の下痢は、アルコールの利尿作用と相まって脱水を促進するため、十分な水分補給が重要です。
【菌ケア的に選ぶなら】からだ想いの良質なお酒4選

前項の下痢の原因を考えると、お酒の飲み方や、とり合わせるおつまみの脂肪分・塩分・糖質などもダメージに加勢している可能性があります。
そして、お酒の製法そのものにもヒントがあるのです。
基本的にアルコール自体は腸内環境にあまりよいものとは言えません。しかしどうしても、お付き合いなどでお酒を飲む機会もあるもの。
頻繁に飲みすぎないことは前提としつつ…製法や成分などを踏まえ、菌ケア的に選ぶならこれ、と思えるお酒の種類を、4つ見ていきましょう。
腸活目線で選ぶヘルシーおつまみについてはこちら▼
マッコリ

マッコリは韓国の有名なお酒の一つと言えますが、韓国のどぶろくとも言われ、白濁した様子と柔らかい飲み口が特徴です。米を主に、麦、あわ、サツマイモ、ジャガイモなどを原料にした醸造酒のマッコリは、100mlあたり44kcalと低カロリーなのもポイント。
特に過熱していない「生マッコリ」では乳酸菌が豊富で、良質のものではたくさんの生きた乳酸菌だけでなく、栄養価も高いとされています。
こちらの生マッコリは、人工甘味料などを一切加えず米本来のほのかな甘み、乳酸菌飲料のような かすかな酸味が特長です。たんぱく質、葉酸、クエン酸、食物繊維も豊富なのだそう。
やはりキムチなど同じお国柄の発酵食品を合わせながら「チャーン」(乾杯の音頭)とやりたいところですね。
芋焼酎

製造法としては蒸留酒に分類されますが、焼酎には昔ながらの製法で一度に少しずつしか生産ができない【乙類】と、大量生産のために新しい製法でアルコールを抽出したクセのまったくない【甲類】があります。
芋焼酎の場合は、原料のサツマイモを原料に発酵させたもろみを単式蒸留器で生成したものが乙類。単式なので一度しかアルコールが取り出されず、風味やクセが強く出るのが特徴。
そしてサツマイモを先に糖化させ発酵させたもろみを蒸留塔というものに入れてアルコールを連続で抽出し、サワーなどで使うため、クセの全くない無色透明な状態の焼酎として作られたものが甲類です。
腸活的に選ぶなら、乙類。乙類のタイプの焼酎はチェイサー(水)を用意して少しずつ味わうことがほとんどであるため、人工甘味料や着色料などの添加物を加えられがちな甲類の焼酎に比べ、乙類の本格芋焼酎はシンプルな成分と考えられます。
焼酎は比較的低カロリーで、糖質やプリン体が含まれないのもポイントです。
こちらの「中村酒造場」によるAmazing seriesはパッケージも芸術的なだけでなく、1888年創業の石造りの麹室に生息する「室付き麹」を使用するなど発酵の過程にまでこだわり尽くした焼酎です。
ワイン

ワインにも赤、白、ロゼと種類がありますが、腸活・菌ケア的には赤ワイン。
さらに甘口と辛口で言えば辛口のものの方が血糖値が上がりづらく、ポリフェノールが豊富なのでより良いと言えます。
赤ワインの健康効果については様々な研究もされており、特に赤ワインポリフェノールによる動脈硬化症に対する作用については論文も多く発表されているようです。
試験管内の細胞に対して行われたある研究では、赤ワイン ・ポリフェノールは動脈硬化症を予防すると共に、動脈硬化症の進行も防止する、という可能性が示唆されていました。(※4)
もちろん大量に摂取をすれば元も子もない話なので気をつけたいですが、適量のワインは身体にとっても嬉しい役割を果たしてくれるかもしれません。
こちらはブドウ栽培から、化学肥料などを一切使わないビオロジック農法にこだわり製造されているワインです。
日本酒

日本酒は醸造酒なので糖質を多く含みますが、他のお酒に比べて、嬉しいことがあります。
それは、グルタミン酸やアルギニンなどのアミノ酸を多く含んでいること。
同じ分量の他のお酒に比べて約2倍のアミノ酸を含んでいます。
アミノ酸はコラーゲンなどタンパク質の原料になるため、保湿の必要なお肌にも大切な栄養です。
なかでも醸造アルコールを加えられていない、純米酒のほうが栄養豊富であると考えられています。
こちらの寺田本家「むすひ」は、日本酒の中でも珍しい発芽玄米酒。酵母や微生物たちが瓶詰め後も生きており、徐々に味も変化していくという「菌」のチカラを感じられるようなお酒です。
大前提は「飲みすぎない」お酒は楽しく適量に

日々のケアから守り育ててきた大切な腸内フローラバランス。そんな菌たちになるべくダメージを与えないようなお酒の飲み方を意識すべく良質なお酒を紹介しました。
お酒を飲みすぎないことはもちろんですが、揺らぎにくい身体づくりには普段からの菌ケアが大切。日頃から腸内環境を意識した食生活を送り、たまの飲酒にはできるだけ添加物の少ない良質なお酒を、ほどほどに。
今回ご紹介したお酒を選んでも飲み過ぎてしまっては意味がないので、量より質。良く味わって適度に楽しんでくださいね。
日常的な腸活習慣についてはこちらでマスターしましょう▼
【参考文献】
(※1) 『病気にならない、太らない、若返る 「腸」が喜ぶお酒の飲み方』著・藤田 紘一郎
(※2)科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究
(※3)科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究「飲酒と大腸がんリスク」
(※4) ブドウとワインに含まれるポリフェノール類の健康効果 ISSN 03695247,佐藤,充克,発行元 [発行元不明],93巻4号,掲載ページ p. 296-308,発行年月 2018年4月
記事の監修

岡山大学歯学部を卒業後、都内医療法人の理事長(任期4年3ヶ月)を務める。クリニック経営を任されながらも、2,500名以上の慢性疾患に対する根本治療を目指した生活習慣改善指導などを行う。
医療法人時代の日本最先端の研究者チームとのマイクロバイオーム研究や、菌を取り入れることによって体質改善した原体験をきっかけに菌による根本治療の可能性を感じ、2018年12月に株式会社KINSを創立。2023年8月にシンガポールにて尋常性ざ瘡(ニキビ)に特化したクリニックを開院。
INSTAGRAM : @yutaka411985 , @yourkins_official
X : @yutaka_shimo